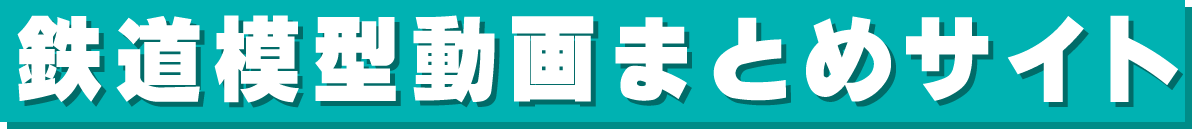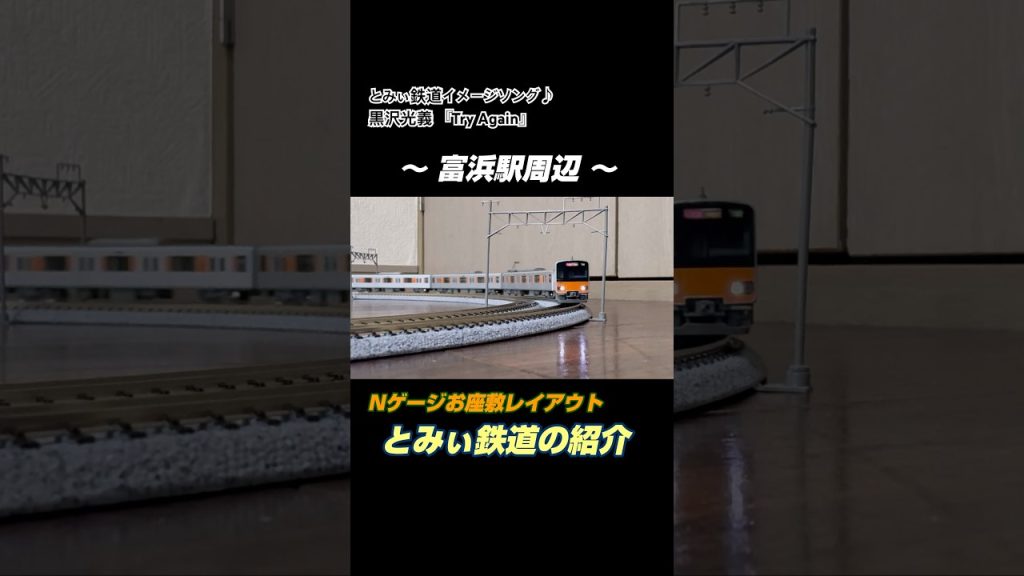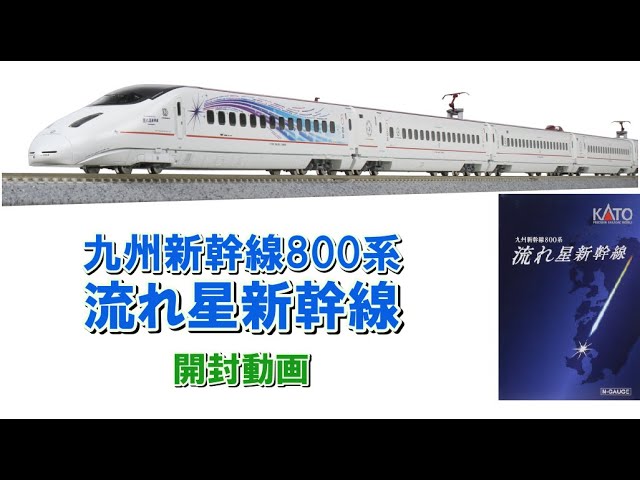鉄道模型の最安値を探す!

おすすめの鉄道模型動画
この動画では1960年頃にキハ25形を使用して運行されていた準急「しんじ」の姿を再現しました。通常はキハ25形3両で運行されていたようですが、今回はキハユニ26形を加え4両編成としました。
国鉄キハ20系気動車は、国鉄が1957年(昭和32年)に開発した一般形気動車です。なお、「キハ20系」という呼び方は国鉄制式の系列名ではなく、キハ20形と同一の設計思想で製造された形式群の総称です。1966年(昭和41年)までに系列合計で1,126両が製造され、日本各地で広く使用されました。
本系列が開発された1950年代中期の時点では、国鉄では普通列車用気動車として17系(当時はキハ45000形一族、現在では10系とも通称)が製造されていましたが、これらは当時の一般的な20 m級客車と比較して車体断面が小さいために居住性が犠牲となっており、乗り心地の点でも問題がありました。
これは、当時国鉄で気動車用として利用可能であった最大のディーゼル機関であるDMH17形の出力では、通常車体断面の20 m級車体とした場合、重量過大に伴う出力不足で十分な走行性能が得られなかったがゆえの苦肉の策であり、そればかりか当時の車体設計手法では小車体断面化だけでは出力不足を補いきれず、客室内の各座席の座り心地を犠牲にした軽量化、あるいは乗り心地が悪いことを承知の上での軽量設計台車の採用など、ありとあらゆる手段を講じてようやく実用性能が得られている状況でした。
しかし、1955年(昭和30年)の10系軽量客車の完成で状況は一変しました。スイス国鉄流の準モノコック構造車体と、プレス鋼板による溶接組立台車の導入により、十分な強度を維持したまま、従来比3/4程度の大幅な軽量化が可能となり、これにより、非力な既存エンジンのままでも大型車体を備える気動車の製造に目処が立ったのです。
こうして、10系客車の設計ノウハウを有効活用する形で、翌1956年(昭和31年)に大断面車体を備える21 m級気動車の第一陣として、準急形気動車であるキハ55系(当時はキハ44800形一族)が製造され、ここに初めて電車・客車と同等の車体(車内設備)を備える気動車が実現しました。
その後、キハ55系の成功を受ける形で、普通列車に用いる一般形気動車についても大型車体へ移行することが決定され、同形式に準じた設計で新たに開発されたのが本系列でした。
両運転台のキハ20形(409両)、
片運転台のキハ25形(142両)、
寒地向け両運転台のキハ21形(84両)、
酷寒地向けデッキ付き両運転台のキハ22形(313両)、
勾配線区向け2個エンジン両運転台のキハ52形(112両)、
寒地・酷寒地向け郵便荷物二等合造車片運転台のキハユニ25形(7両)、
暖地向け郵便荷物二等合造車片運転台のキハユニ26形(59両)
の合計1,126両が1957年から1966年までに製造されました。
車体は先行するキハ55形の設計が踏襲され、柱や梁だけではなく側板なども強度を分担する準張殻構造となり、キハ10系より大型化され、客車並みの大断面となりました。また、従来の反省から、客ドア位置も車体中央寄りに配置され、ラッシュ時の客扱いに配慮されました。座席も車体幅拡幅を受けて準急形に準じたゆとりのあるものとなりました。客室内を通る排気管のキセ(覆い)はキハ55 1 – 46などと同様に大型のタイプとしました。暖房装置は燃焼式の温気暖房となっています。
客室窓はキハ10系のそれを踏襲して、上段がH断面ゴムによる構体直接固定、下段が上昇式の俗にいう「バス窓」です。しかし、キハ10系とは異なり、窓下のウィンドウシル(補強帯)は廃され、平滑な外観となりました。
初期車竣工当初の車体塗色は、当時の気動車標準色である濃い青(青3号)+ 窓周りが黄褐色(黄かっ色2号)のツートーンでした。また当系列においては前面幕板部の塗色が前照灯部分に回り込むように塗装されていることが他系列には見られない特徴となっています。
機関は当初はキハ10系と同様にDMH17B形ディーゼルエンジン(160 PS)を搭載しました。燃料噴射ノズルなどの改良でキハ10系より10psアップの170ps仕様とし、さらに後年その大半が180psのDMH17C形相当に改造または換装されました。
台車は、初期型はキハ10系と同様の防振ゴムブロックを枕バネに使用するウィングバネ式DT19C(駆動台車)・TR49A(付随台車)を装着しました。後年には増備車と同様にコイルバネ+オイルダンパを枕バネとするDT22A・TR51Aに交換されたものがありました。
1958年の増備車からは機関を180psのDMH17Cに変更して走行性能を改善し、台車は従来のDT19で使用されていた硬い防振ゴムブロックに代えて複列コイルばねを枕ばねに使用した揺れ枕吊り台車とし揺動特性を改善したDT22A(駆動台車)・TR51A(付随台車)に変更することで大幅な乗り心地の向上が実現しました。
車体の部材を専用のプレス品から市販の形鋼に変更し、調達コストの低減が図られました。また、客室窓が2段上昇式(上下段共に上昇式)に変更され、より近代的な外観となり、客室内の採光や換気も改善されたほか、排気管キセが小型化されて見通しがよくなりました。
この際、派生形式として北海道向け耐寒耐雪強化仕様のキハ22形、郵便荷物合造車のキハユニ26形、そしてエンジンを2基装架する勾配線区向け強力形のキハ52形などが新たに設計されました。キハ20形・キハ25形もこの増備車よりキハ20形200番台・キハ25形200番台に区分されています。
なお、このグループの初期車は室内灯として白熱灯を装備し扇風機無しで製造されたが、バス窓の初期形を含むその多くが後年に環形蛍光灯仕様に改造し扇風機の取付もされました。暖房装置はキハ22形では温水暖房に変更され、キハユニ26形では温気暖房と温水暖房が併設されました。
なお、1959年9月から一般形気動車は、外板色をそれまでの青系から、朱色4号の地色に、窓周りをクリーム4号の塗り分けとした新塗色へ移行しました。
準急「しんじ」は、1960年(昭和35年)3月15日岡山~出雲市間(伯備線経由)でキハ25形により運行を開始しました。列車名は宍道湖からとられました。
1961年(昭和36年)10月改正では、「しんじ」は宇野~益田~下関~博多間(益田~下関間は山陰本線経由の便と山口線経由の便の2ルートで分割併合運転)に延長されました。
1962年(昭和37年)3月からは車両はキハ55系化され、「しんじ」は準急「しらぎり」(広島~米子間・芸備線経由)および準急「たいしゃく」(岡山~広島間・芸備線経由)と併結運転されました。同年9月からは宇野~岡山間で準急「砂丘}(宇野~鳥取間・津山線・因美線経由)も併結されるようになりました。そして1966年(昭和41年)3月、全国の準急列車は一斉に急行化され、「しんじ」も急行となりました。